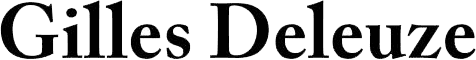
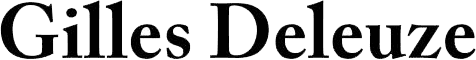
差異と反復
(1992.2007.河出書房新社)
10年にわたり、ドゥルーズの自らの主題に関連した近代の哲学史上の哲学者についてのモノローグを発表しながら、自身の「問題」について問いつづけその徹底的な解を与えた書物が、ドゥルーズの国家博士論文として結実したこの「差異と反復」である。
ドゥルーズの前出著作のモノローグとは異なり、対象とする他の哲学者の言説から自由になって、ドゥルーズ自身の本格的な練り上げられた自説を述べた書物であり、後続の著作で発展したた後にも、常に必ず原点であるこの著作に戻ってくる書物である。誤解なく叙述するためいささか冗長な長文ながら、忠実に論行を跡ずけることに主眼を置いて以下叙述する。
はじめに
「同一性をどのように理解しようとも、いずれにせよ同一性の優位によって表象=再現前化の世界が定義される。」(単行本p21)だが「わたしたちは、それ自身における差異をそして<異なるもの>と<異なるもの>との関係を、表象=再現前化の諸形式から独立して考えたい。なぜなら、この形式は、その差異とその関係を<同じ>ものに連れ戻し、それをして否定的なものを経由させてしまうからである。」(p14)「諸問題がおのれに固有な定立性の段階に達するとき、また差異がその段階に対応した肯定の対象となるとき、その諸問題は、ある攻撃と選別の力を解き放つのである。」(p15)「この場合の闘争と破壊とはそれに比べれば否定的なものの闘争や破壊が仮象にしかならないような」「闘争、破壊である。」(p15)「経験論とは未見にして未聞のこのうえなく発狂した概念創造の企てである。」
「しかし経験論は、概念をまさにある出会いの対象として<ここ?いま>としてあるいはエレホンとして取り扱う。」(p15)「私たちは起源的な『どこにもないもの』と置き換えられ、偽装され、変容され、常に再創造される『ここと今』を同時に意味するものとしてエレホンを発見するのである。もろもろの経験的な個別性でもなければ抽象的普遍でもないもの。崩潰した自我として<私は思考する>。私たちはどの個体化も非人称的であり、どの特異性も前個体的であるひとつの世界を信じる。<ひと(on)>それはなんと素晴らしいものであろうか。そこにこそ」「この書物が現前させるべきであったこと、それは以上からして神のものあるいは世界のものでもなければ、私たちのもの、すなわち人間のものでもないようなある一貫性へのアプローチである。」と述べる。ドゥルーズは我々の時代のある種の固定観念であるようなものと対比して「ポスト・ヒューマニズム」について述べようとしており、デカルト的コギトとは、別の場所に個体化の場を見出す。
序論
○反復と一般性との行動の視点からする第一の区別
「一般性はどの項も他の項と交換可能であり、他の項に置換しうるという視点を表現している。」(p19)「反復は代理されないもの〔かけがえのないもの〕に対してのみ必然的で根拠のある行動になるということがよくわかる。行動としての、かつ視点としての反復は交換不可能な、置換不可能な或る特異性に関わる。」(p19)反復は行動においてはその都度ユニークなものであり、反復される行動はその都度1度きりのものである。「権利上価値あるものというのは、二回目、三回目を経る必要のないたった一回の力=累乗としての「n」回のことである。」(p22)
○法則の視点からする第二の区別
「反復は法則に反している。すなわち、法則の類似形式と等価内容に反しているのだ。反復が自然の中にさえ見出されうるのであれば、それは、法則なるものに反する自己を肯定し、諸法則の下で働き、おそらくは諸法則に優越するような、そうした力の名においてである。」(p21)物理学の「実験においては、問題になるのは一般性のひとつのレベルを他のレベルに置換すること、つまり類似のレベルを等しさのレベルに置換することである。実験の個別的な諸条件のなかでひとつの現象を同定するのを可能にしてくれる等しさを発見するために諸類似をこわすということだ。」「反復は、たとえ現れ出るために、ひとつの一般的なレベルからもう一つのレベルへの人為的移行を利用するにしても、その本質においては、本性上一般性とは異なる特異な力=累乗を指し示しているのだ。」(p21)「道徳法則によっては、わたしたちは真の反復を得るどころか、反対に、またもや一般性の中にとどまってしまうのである。この場合、一般性は、もはや自然の一般性ではなく、第二の自然としての習慣の一般性である。」「習慣が身につくや、行動の諸要素が、色々な状況にあっても等しくなるということである。だから習慣は、決して真の反復を形成することがない。」(p24)
○キルケゴール・ニーチェ・ペギーによる反復の哲学のプログラム
「この三人は、それぞれ、それなりの流儀で、反復を、言語と思考の一つの本来的な力に、ひとつのパトスに、そしてひとつの高次の病理学に仕立て上げたばかりでなく、さらに未来の哲学の基本的なカテゴリーにまで仕立て上げたのである。」(p25)行動の観点から「反復を新しいものにすること」法則の観点から「反復を自然法則に対置すること」道徳の視点から「道徳法則に対置すること」さらに「反復を習慣に属するもろもろの一般的なものを対置するだけでなく記憶に属するもろもろの個別的なものに対置すること」を提唱する。(p26〜p29)「キルケゴールとニーチェは形而上学を運動させようと、活動させようと欲している。彼らは形而上学を現実態に移行させようとそして直接的な諸行為に移行させようとしている。」「表象=再現前化はそれだけですでに媒介であるからだ。逆にあらゆる表象=再現前化の外側で精神を揺り動かしうる運動を作品の中で生産することが必要なのである。」(p29)「演劇、それは現実的運動である。そして演劇は、おのれが利用するすべての芸術から、現実的運動を引き出す。だからこそ、そうした運動は、というよりその運動の本質と内的性格は、反復であって、対立ではなく、媒介でもないと、ひとは私たちに語るのである。」(p31)
○概念の視点からする第三の区別
「さらに概念のあるいは表象=再現前化の視点から」「権利問題としてのひとつの問いを以下のように立ててみよう。」概念が「ひとつの存在する個別的な事物の概念であることが可能であり、その際無限な内包をもつ。」さらに「無限な内包は外延=1と相関している。」「そうした概念の無限性は現実態における無限性として定立されている」のであり、「以上を条件としてはじめて概念の契機としての諸述語はそれら述語が帰属する言語の中で保存され有効になる。こうして無限な内包は想起と再認つまり記憶と自己意識を可能にする。概念とその対象との関係はそのような二つのアスペクトのもとですなわちそうした記憶とそして自己意識のなかで実現されているようなものとして表象=再現前化と呼ばれる。」これがドイツ観念論におけるカントからヘーゲルにいたる「自己意識」を保証する諸前提である。
「しかしどの概念であれ、その概念のそれぞれの規定の水準において、つまりその概念に含まれるそれぞれの述語の水準においてつねに阻止される可能性がある。」(p34)とドゥルーズは述べ、概念の人為的阻止における論理学と、3種の自然的阻止について先験的論理学あるいは、ひとつの弁証論を論述する。これによって表象=再現前化が阻止されることを論証する。すなわち「自然的阻止の三つの事例として」名目的諸概念、自然の諸概念、自由の諸概念を挙げる。
「有限な内包をもった諸概念は名目的概念であり、他方無際限的な内包はもつが記憶はもたない諸概念は自然の概念である。」さらに「無限な内包を持ち、記憶をそなえているが自己意識は持たない個人的観念」としての自由の概念について論じられる。(p37)
「第一の事例では名目的概念が有限な内包を本性上持つがゆえに反復が存在する。」(p39)「概念に関しては絶対的に同一でありながら現実存在においては特異性そのものの性格を帯びているような諸個体の繁殖がみいだされる」(p35)こととなり、「第二の事例では自然の概念が本性上記憶を欠き疎外され、自己の外にあるがゆえに反復が存在する。第三の事例では自由の概念が無意識的なままであり、追想と表象=再現前化が抑圧されたままであるがゆえに反復が存在する。」(p39)「それらすべてのケースにおいて、反復をなすものは「理解」しないからこそ、追想しないからこそ、知らないあるいは意識しないからこそ反復をするのである。」(p40)
「しかしながら概念の同一性の形式にもとづくあらゆる論証に関する欠陥は」「反復についての名目的定義および否定的説明しか与えてくれないということだ。」
○死の本能と反復の定立的原理
「死の本能は、反復にとって、本源的な定立的原理の価値を持つのであってまさに反復にこそ死の本能の本領と意味があるのだ。」(p40)「死の本能を仮面や仮装との関係において理解すれば」「反復はまことに構成されるがゆえに偽装されるもの、偽装されなければ構成されないものである。」(p41)とのべ、起源なき絶えざる置き換えと偽装を反復とみなす。
○概念の同一性と否定性による反復と、差異による、そして<理念>における過剰による反復
「いずれの形式においても、反復とは、概念なき差異のことである。しかし一方においては、差異は概念に対して外的な差異として、換言すれば同じ概念のもとで表象=再現前化されるものであり、」「他方においては差異は<イデア>の内部に存在している。この差異は理念に対応するある動的な空間と時間を創造する純然たる運動としておのれを展開する」のである。(p50)
○概念的差異と概念なき差異
「内的発生のエレメントは、私たちには図式よりもむしろ内包量にあり、悟性概念よりもむしろ<理念>(イデー)に関係していると思われる。」(P54) 「差異の概念(イデア)は概念的差異に還元されることはなく、同様に反復の定立的な本質は概念なき差異に還元されることはない。」(p55)そして差異の概念とはどのようなものか、反復の本質はどのようなものであるか、が以下本論で述べられる。
第一章
○「無差異には二つのアスペクトがある。」「一方の未規定なものは、まったく無差異であるが、しかし他方の浮遊する諸規定も、未規定なものに劣らず、互いに無差異的である。」しかし「差異こそが唯一の極、すなわち、現前と明確さの唯一の契機ではないだろうか。差異とは、そこで規定作用そのものを語ることが可能になる当の状態なのである。」「ひとつの事物が他の事物から区別されるという事態のかわりに、何らかのものが際立つ(一方に区別される)という事態を想像してみよう。」「背景は背景であるがままに表面に出てくる、とでも言えそうである。」「差異とは一方的な区別<際立ち>としての規定作用の以上のような状態なのである。」(単行本p57)「だが実をいえば、浮き出る背景に反映するとき、散乱するのはまさしくすべての形<形相>である。」「浮き出る背景はもはや背後に退いてはいず、自律的な存在を獲得するのであり、そのような背景に反映する形は、もはや形ではなく、直接魂に訴えかける抽象的な線になる。」「おのれの威力のすべてを手に入れる抽象的な線はおのれが背景から際立ちながらも背景はおのれから際立たないだけに、いっそう激しく背景に関与してしまうのである。」「思考とは、そこにおいて規定作用が、未規定なものとの一方的で明確な関係を維持することによってはじめてひとつに規定へとつくりあげられる、当の契機だからである。」(同p58)
「差異は一つの形式においてすなわち有機的な表象=再現前化の首尾一貫したエレメントにおいて、規定作用そのものを他の諸規定に関係させることができるのではないだろうか(と思われている)。」充足理由の4つのアスペクトは媒介の四つの諸形式である、「同一 性と対立、類比と類似という四重の根に首尾よく差異を服従させてしまうかぎり、人は差異は表象=再現前化において媒介されているというだろう。」
「してみると、問題は、差異がいわば概念と和解している幸福な契機一をギリシャ的な幸福な契機一を規定することにある。」(p59)
○「本質あるいは形相における反対性のみが私たちに、それ自体本質的な差異という概念を与えるのであ」り、「完全で最大の差異は(アリストテレスにおいては)類における反対性であり、類における反対性とは結局、種的差異のことである。」「そのような差異はいたるところで単純な異他性に帰着する傾きがあり、概念の同一性を免れているのである。類的差異はと言えば、それは、大きすぎる差異であり、反対性の関係には入ってこないような、組み合わせ不可能なものどもの間の差異である。個体的差異は小さすぎる差異でありこれもまた反対性をもっていない分割不可能なものどもの間の差異である。」(p61)
種的な差異は、それ自身とともに、類(類と種の体系における)すべての中間的な差異を運搬していく。」「すなわち種別化は差異を差異によって分割の相次ぐ諸水準に繋ぎ止めてゆき、その結果、最後の差異、すなわち最低種という差異が本質とその連続的な質との総体をひとつの直観的概念にまとめ上げその総体を定義さるべき名辞を用いて確立し、こうして最後の差異自身が不可分の唯一のものになる。このよううにして種別化は概念の内包における 一貫性と連続性を保証しているのである。」「種的差異は、したがって、すべての特異性と、差異のすべてのあの転回にとっての、ひとつの普遍概念すなわちひとつの<イデア>を表象=再現前化することは決してなく、かえって、差異が概念一般と和解しているだけのひとつの幸福な契機を示しているのに過ぎないのである。」(p62)「差異の本来的な概念<イデア>を定めるということ、概念一般の中に差異を刻み込むということと混同するということ、一差異概念を規定することを、未規定な概念(類)の同一性に差異(種差)を刻みこむことと混同するすることいえるだろう。差異をそのように刻み込むなどというのは、幸福な契機における手品である。」(p63)
以下の論行において、アリストテレスの哲学の種的差異と類的差異の方法が検討され、 「まるで本性上異なりなりながらもたがいにもつれあっている二つのロゴスが存在するかのようにすべてが進行してゆく。」すなわち「種のロゴス」は「類とみなされる概念一般の同一性あるいは一義性という条件のもとで成立しているのである。」他方「類のロゴス」は「右の条件から解放されており」「存在の多義性の中でも活動しているのである。」「そして思考の中にもたらされた一種の亀裂を、しかも別の(非アリストテレス的な)雰囲気のなかに陥乳してゆく一種の亀裂を見てとるべきではないだろうか。」(p64)
そして、いかにして反省概念としての差異が「概念における同一性、諸述語に関する対立、判断の関する類比、知覚に関する類似」に服従し「有機的な表象=再現前化」が生成するかが述べられる。「差異が反省概念であることをやめ、現実的に実在的な概念を取り戻すのは、その差異が、たとえばもろもろの類似のセリーにおける連続性の断絶や、類比的な諸構造の間の越えがたい裂け目といったカタストロフを指し示すかぎりにでのことでしかないのである。」(p66)○存在の「一義性の本質的な点は<存在>がただひとつの同じ<意味>において言われるというところにあるのではない。その本質的な点は<存在>がただ一つの同じ<意味>において己の個体化の諸差異つまり本質的な諸要素について言われるというところにあるのだ。」「なるほど一義的な存在において、またもや個体化の諸ファクターとそれらの意味に関わるひとつのヒエラルキーと一つの配分が見いだされる。」(p69)「ノマド的と呼ばなければならない配分、すなわち所有地もなければ囲いも限度もない遊牧的なノモス」については「定住的な空間とは対照的な遊びの空間、定住的なノモスとは対照的なゲームの規則が語られるであろう。」「存在の一義性は、したがって存在のそのような等しさ(平等)をも意味する。一義的な<存在>は、遊牧的配分であると同時に、戴冠せるアナーキーであるのだ。」(p71)
「類似は、何がそれら存在者の個体性を構成しているのかについては言うことはできないのである。」表象=代理現前化の一般的可能性に条件ずけられることなく「一義的な存在は諸々の個体化のファクターに本質的にかつ直接に関係するというとき」「経験において構成された個体ではなく、むしろ個体において先験的原理として、すなわち、個体化のプロセスと同時的な、アナーキー的でノマド的な可塑的原理として作用しているものである。」(p72)
哲学史における存在の一義性の「第一の契機は、ドン・スコトゥスによって代表されるものである。」(p74)「第二の契機はスピノザであって、彼の進歩には著しいものがある。彼は、一義性を中立的なあるいは無差異的なものと考えるかわりに、一義的存在を純粋な肯定の対象に仕立て上げる。一義的存在は、唯一の普遍的なそして無限な実体と溶け合って一つになっている。すなわち、一義的存在は、<神即自然>として定立されている。」「一義的存在が中立化されなくなり、そして表現的になり、ひとつの真の肯定的な表現的命題へと生成するのは、まさにスピノザにおいてである。」(p75)
存在の一義性の第三の契機はニーチェによるものである。「実体は、それ自体諸様態について言われ、しかも諸様態についてのみ言われるという条件が必要になるだろう。そのような条件が満たされうるのは、存在は生成について言われ、同一的なものは異なるものについて言われ、一は多について言われる等々となるようなより一般的なカテゴリーの逆転という代償を支払う場合だけである。そのような条件が満たされうるのは、存在は生成について言われ、同一性は異なるものについて言われ、一は多について言われうる等々となるような、より一般的なカテゴリー上の逆転という代償を支払う場合だけである。同一性は最初のものではないこと、なるほど原理として存在するが,ただし二次的な原理として、生成した原理として存在すること、要するに同一性は<異なるもの>の周りをまわっているということ、これこそが、差異にそれ本来の概念の可能性を開いてやるコペルニクス的転回の本性であ」る。(p76)「力の意志のいくつもの変身と数々の仮面の演劇的世界についてのみ、」「永遠回帰が言われるのである。」「永遠回帰、つまり環帰が表現しているのは、すべての変身に共通な存在であり、またすべての極限的なもの、あるいは実在化された度である限りでの力のすべての度の限度および共通な存在である。」「すなわち誰もがヒュブリス(傲慢・度を越すこと)においてこそ、そのヒュブリスを喚起させる存在を見出すのだ。」 「永遠回帰とは存在の一義性のことであり、この一義性の現実的な実在化のことである。」(p77)
○差異とオルジックな表象=再現前化
ヘーゲルにおける差異の対立の極大とライプニッツにおける無限小「によるテストは概念一般の同一性の諸要請を利するために再の本来的な概念を放棄してしまうので私たちには選別を歪曲してしまうもののように思われた。」「「差異を作ること(差をつける)」ということを本領とする選別は私たちには別の意味を持つように思われたのである。すなわち、有機的な表象=再現前の諸要請に従って中間的な諸形式の真価を測り、それらを割り振るというよりはむしろ―ある一義的な存在の単純な現前の中で諸々の極限形式を出現させ展開させるという意味である。」(p78)「表象=再現前化がおのれ自身のうちに無限を発見するときその表象=再現前化はもはやオルガニックな(有機的な)ものではなく、オルジックな表象=再現前化として現れる。」「全体がその恩恵をすべての部分に広げようと、あるいは諸部分の分裂と不幸が一種の赦免を受けるために全体の中に反映しようと、いまや概念は全体になる。したがって概念は、規定のすべての変身においてその規定全体に付き従い結びついてゆき、規定をひとつの根拠にゆだねることによってその規定を純粋な差異として表象=再現前化するので」あり、最大か最小かは「ただひとつの同じ「全体的な」契機としての根拠においてそれら二つのものは合致するのである。」(p79)
「まさに限界(極限)という基礎概念そのものが全く意味を変えるのである。つまり、その基礎概念はもはや有限な表象=再現前化の境界を指し示しているのではない。」「その基礎概念が指し示しているものはもはやひとつの形式の限定ではなくひとつの根拠へ向かっての収束であり、根拠づけられるものと根拠づけるものとの相関関係である。」 それが「指し示しているのはもはや力=累乗の停止ではなく、力=累乗が実現され根拠づけられるエレメントである。事実微分法は弁証法に劣らず「力=累乗」に関わっている。」(p79)
「オルジックな表象=再現前化は原理として根拠を持ち無限をエレメントとしてもつのであり、それに対してオルガニック(有機的・組織的)な表象=再現前化は原理として形式を保持し有限はエレメントとして保存するのだ。規定を、考えうるものに、また選別されうるものにするのは、まさに無限である。」無限がオルジックな表象=再現前化のもとで有限それ自身について言われるかぎり、「確定できない二つの無限なプロセスの二者択一という形で―ライプニッツとヘーゲルの間の二者択一というかたちで―再導入されるのである。」(p80)
「ヘーゲルとライプニッツの差異はオルガニックなものを越える二つの仕方に由来していると思われる。」(p83)「(ライプニッツにおいては)非本質的なものは、本質的なものを、事例において包含するのだが、(ヘーゲルにおいては)本質的なものは、非本質的なものを、本質において包含するのである。」(p84)
差異的=微分的な関係=比は「相互規定と十分な規定という二重なアスペクトのもとではすでに、限界=極限が力=累乗そのものと合致していることが明らかになる。限界=極限は収束によって定義されるものである。関数のもろもろの数値は、おのれの限界=極限を、差異的=微分的な関係=比に見出し、もろもろの差異的=微分的な関係=比は おのれの限界=極限をもろもろの<変化の度>に見出す。そして、それら<変化の度>のそれぞれにおいて、特別な点(特異点)が、解析的に互いに接続しあっているもろもろの級数の限界=極限をなしているのである。」(p85)ヘーゲルにおいてもライプニッツにおいても「諸本質のたんなる類比から、あるいは諸固有性の単なる類似から差異に関する思考を独立させるためには、無限な表象=再現前化だけでは不十分であるように思われる。なぜなら、結局のところ無限な表象=再現前化といえどもその表象=再現前化の前提としての同一性の原理から解放されていないからである。」(p88)
○差異には決裁的実験がある。言い換えるなら、私たちが限定に直面したりあるいはそれに陥ったりするたびごとに、また、対立に直面したりしたりそれに陥ったりするたびごとに」「そのような状況の前提として差異のひしめき、野生的なあるいは飼い馴らされていない自由な差異の多元性、限界と対立という単純化にあっても執拗に存続するような本源的でしんそこ差異的=微分的な時間と空間といったものが存在するのである。諸威力の対立あるいは様々な形の限定がはっきりと現れるためには、まず初めに、非定型で潜勢的な多様体として定義され、規定されるようないっそう深い実在的なエレメントがなければならない。」が諸限定、諸対立の、いずれの場合にも「私たちの手から逃れていくものが存在するのであって、それが空間全体の母胎でもあれば際の最初の肯定でもあるような強度的な、根源的な深さなのである。」後にドゥルーズはこの時空間を生成させる実在的なものを強度的多様体として定義する。(p90)
「差異哲学が拒絶するのは「スベテノ規定ハ否定デアル」ということだ。無限な表象=差異現前化に関する一般的な二者択一、すなわち、未規定なもの、無差異的なもの、未異化=未分化のものか、あるいはすでに否定として規定され否定的なものを巻き込み包み込んでいるものとしての差異かといった二者択一が拒絶されるのである。」(p93)すなわち否定について、無限は有限な規定の否定であるとも、無限なものの否定によって限定される有限性についても、いずれもが排除されるのである。限定は極限としての無限漸近的な収束であり、否定性ではない。
「肯定が最初のものである。つまり、そうした肯定においては、差異、距離、肯定されるのである。差異は軽やかなもの、空気のようなもの肯定的なものである。」それはニーチェの言う<騾馬の然りと否・ディオニュソス―ツアラストラの然りと否>のごとく、「肯定することは担うことではない。反対にそれは荷を降ろすこと、軽くすることなのである。」オルジックな表象代理現前化におけるように、「無限な表象=再代理現前化のなかで偽りの肯定をしてみたところで、わたしたちは中間的な諸形式の外に出られるはずもない。」(p96)「真の選別を行うことが永遠回帰の役割であると言えるのは、永遠回帰が、反対に中間的な諸形式を排除し、「存在するものすべての最高の形相」を取り出してみせるからである。極限的ということは、反対なものどうしの同一性のことではなく、むしろ異なるものの一義性のことである。高次の形式とは無限な形式のことではなくむしろ変身と変態を貫通する永遠回帰それ自身の非定型の永遠性のことである。永遠印回帰が差異をつくるといわれるのはそれが高次の形式を創造するからである。」(p96-97)「定立的な差異的=微分的諸エレメントが存在するのであって、これらのエレメントにおいてこそ、肯定の発生と肯定される差異の発生とが同時に規定されるのである。わたしたちが、肯定を未規定なものの中に放置してしまえば、あるいは規定を否定的なもののなかにおいてしまえば、わたしたちは、肯定そのものの発生が存在するという事態をそのたびごとに見逃してしまうのである。」「否定は肯定から帰結する」ということは「肯定と肯定における差異とを産出する力のあるいはそれらを産出する「意思」の影として出現するということである。」(p98) 「視点のそれぞれが、それ自体事物でなければならないし、あるいはまた、事物は事物はそのような視点に属しているのでなければならない。したがって事物はけっして同一的な、ものであることができず、見られる対象の同一性も見る主体の同一性も同様に消失するような当の差異の中で、事物は八つ裂きにされているのでなければならない。」(p99)「反復とは、すべての差異の非定型的な存在であり。また、表象=再現前化が壊されてしまうような極限形式にあらゆる事例をもたらす基底のもつ非定型的な力のことである。齟齬をきたすもの(差異)とは表象=再現前化の同一性と対立する反復の究極のエレメントである。」(p98)「永遠回帰が最高度の思想であるのは、換言すれば、最も強度の高い思想であるのは、永遠回帰の極限的な一貫性が、最高度の点において思考する主体(主観)、思考される世界、さらに保証する<神>のそれぞれの一貫性を排除するからである。」カントが理性的神学を批判するとき「権利上克服できない正当な疎外を<私は考える>に純粋な<自我>の中に導きいれ」る。「すなわち主観は自分自身の自発性を、もはや<他.>なるものの自発性としてしか表象=再現前化することができず、したがって結局のところ、主観自身の一貫性、世界の一貫性、および神の一貫性と相容れない神秘的な一貫性を援用するのである。」「私たちがほんの少し立ち入って考えてみたのは、思考の最高度の力の特徴たる正当な精神分裂症である。これは概念によるすべての媒介やすべての和解を一顧だにすることなく、<存在>をダイレクトに差異へと開かせるものである。」(p102)
○ 現代哲学の責務は「プラトン哲学の転倒」として定義された。ところが、プラトン哲学の転倒には、数多くのプラトン哲学の特徴が保存されているのであって、これは、たんに避けることができないというだけでなく、望ましい事態でもある。」(p102)「イデアはまだ世界を表象=再現前化に服従させるようなひとつの対象概念ではなく、むしろ、或る野生の現前なのであって、それは、諸事物のうちにある「表象=再現前化されうる」ことのないものに応じてしか、世界のなかに呼び出されえないものなのである。」「差異のディアレクティックには、それ固有の方法がそなわっているのだが、この分割は、媒介なしに、媒概念あるいは理由なしに働き、こうして概念一般の諸要請というよりはむしろ、<イデア>の霊感を頼みにしているようである。」「その(分割という)方法は<イデア>の観点からすればまさにそのイデアの観点からすれば、まさにそのイデアの威力ではないだろうか。」(p103)「分割は差異をつくることが可能な根拠としての神話を要請し、逆に、神話は根拠づけられるべきものにおける差異の状態としての分割を要請するのである。分割は、弁証法と神話体系との、土台としての神話と分割の理法としてのロゴスとの真の統一である。根拠のそのような役割がまったき明瞭さをもって現れてくるのは分有についてのプラトン的な考え方においてである。」「ひとり<正義(というイデア、つまり根拠)>のみが正しい、とプラトンは言う。」(P107)「つまり様々な度で(正しさを)分有するもの、それが必然的に要求者なのである。」「そうした要求は、他の諸現象とならぶひとつの現象なのではなく、あらゆる現象の本性なのである。根拠とは、要求の対象(正しさ)を分有する可能性をより多くあるいはより少なく、要求者に与えるひとつのテストである。まさにこうした意味で根拠は、真価の測定を行い、差異をつくる(差をつける)のである。」(p108)「ところで根拠によるテストの本質的な内容は正確にはどのようなものであろうか。神話が、その答えをわたしたちに教えてくれる。すなわち、それはつねに、果たさなければならぬ責務、解かなければならない謎である、と。神託にたずねてみても、神託の答は、それ時自体、ひとつの問題なのである。(プラトンにおける)弁証法(問答法)はイロニーであるのだが、このイロニーは、問題および問いに関する技術である。」(p109)「問題と問いは認識における不十分さの契機を示すような欠如的、主観的な規定ではない。問題的な構造は諸対象の側に属しており、その構造のおかげで諸対象をしるし(シーニュ)として捉えることができる。」「問題あるいは問いそのものの本質に「照応している」のはまさに存在である。」「いわば「開在性」「開口」存在論的な「襞」があり、これが存在と問いを相互に関係させている。こうした関係においては、存在は<差異>それ自身である。存在はなるほど非―存在でもあるが、しかし非―存在は否定的なものの存在なのではな異のであって、むしろ問題的なものの存在、問題と問いの存在なのである。」(p110)
ハイデガーについてのドゥルーズの立場が以下述べられる。 「わたしたちは、差異と問いとの、すなわち存在論的差異と問いの存在との」「照応を根本的なものとみなしている。」(p113)
○「プラトン的弁証法の四つの形態はしたがって、差異の選別、円環的神話の創設、土台の設定、<問い一問題>という複合体の定立、ということになる。しかし差異は、それらの形態を通じて、またもや<同じ>ものあるいは<一>に帰着させられてしまう。」(p113)「プラトン哲学の転倒の意味は、コピーに対するオリジナルの優位を否認すること、影象(イマージュ)に対する範型(モデル)の優位を否認することである。」「永遠回帰はそれが存在させ(そして還帰させるもの)を見せかけであるもの(エタン シミュラクル)として性格づける。永遠回帰が<存在> (非定型なもの)の力であるとき、見せかけ(シミュラクル )は存在するもの―「存在者」―の真の特徴あるいは形式になる。」「永遠回帰は、わたしたちを普遍的な「脱根拠化」に直面させるのだ。脱根拠化という言葉によって理解しなければならないのは、まさに永遠回帰を構成する媒介されていない基底の自由であり、他のあらゆる基底の背後に控える或る一つの基底の発見であり無底と根拠づけられていないものとの関係であり、非定型なものおよび最高の形相に関する直接的な反省である。」(p114)「プラトンは最初にプラトンを転倒させるもの」であり、ソピステスにおいて「見せかけを深く究めることによってその見せかけがオリジナルあるいは範型から区別できないということを証明している。」「差異のそれぞれの契機は、おのれの真の形態すなわち選別、反復、脱根拠化、<問い―問題>という複合を発見しなければならない。」「エステティックがもはや他へは還元できない二つの領域に分裂するのも、なんら驚くべきことではない。すなわち、その一方は現実的なものに関して可能な経験に合致するものしか保持しえないよような感覚されうるものについての感性論(エステティック)であり、他方は現実的なものの現実性をそれが反映する限りにおいて取り込むような、美についての理論としての美学である。だが条件づけられるものよりはゆるくはなく、そしてそれらのカテゴリーとは本性上異なっている現実的な経験の諸条件をわたしたちが規定するとき、事態はすべてかわるのだ。」(p116)「さて以上のような方向でこそ、もはや可能な経験の諸条件ではなく、現実的な経験(選別、反復、等々)の諸条件を探究しなければならない。」(p117)
第二章 それ自身へ向かう反復
○ 「反復は、反復する対象に、何の変化ももたらさないが、その反復を観照する精神には何らかの変化をもたらす。」「反復における不連続性と瞬間性の規則を定式化するなら、それは<一方が消えてしまわなければ他方は現れない>と表現することが出来る。」「そのかわり観照する精神のなかにひとつの変化が生じるつまり、ひとつの差異が、つまり、ひとつの差異が、つまり新しいものが精神の中に生じるのである。」(p119) ○ 時間の第一の総合―生ける現在 「そのような変化の本質はどこにあるだろうか。ヒュームは互いに独立した同じ諸事例あるいは似ている諸事例は、想像力の中で融合される、と説明している。この場合、想像力はひとつの縮約の能力は新しいものが現れてきても以前のものを保持している。」「こうした縮約は、絶対に、記憶ではないし、また知性の働きでもない。つまりこの縮約は、反省ではないのだ。この縮約は、厳密に言えば時間の総合を形成するものである。」「「時間は、瞬間の反復に関わる根源的総合のうちにしか構成されない。」「根源的総合は生きられた現在をあるいは生ける現在を構成する。」「こうした現在は過去から未来へ進むためにおのれ自身から抜け出る必要はない。」「生ける現在はおのれが時間において構成する過去から未来へ、それゆえにまさしく個別的なものから一般的なものへ進むのである。」「精神の中に生み出された差異は未来に関する生ける規則を形成する限りにおいて一般性そのものである。」「こうした総合は、どこから見ても、受動的総合と名づけるほかないものである。この総合は、構成を遂行するかといって能動的であるわけではない。」(p120)「反復の構成はすでに三つの審廷を含意している。まず、反復を思考されないままにしておく即自、つまり反復ができあがるそばからそれを壊していく即自。つぎに受動的総合における対自。さらに、この受動的総合に基づきながらも、能動的総合において反省された、「対われわれの」表象=再現前化。」(p121)ここでドゥルーズはベルグソンとヒュームとにおける縮約を取り上げる。ベルグソンにおけるそれは要素によるもの、ヒュームの縮約を事例におけるもの、とする。「(ヒュームとベルグソンにおける)二つの形式の反復はつねに、受動的総合のなかで相互に指し示しあう。すなわち、事例の反復は、要素の反復を前提にしており、要素の反復は、必然的におのれを越え出て事例の反復に向かってゆくのである。」(p122)
「ヒュームの例においてもベルグソンの例においても私たちは感性的な総合および知覚的な総合の水準に身を置くことになる。」「知覚的総合はそれぞれ、構成する受動性のレベルにおいて有機的な総合を示しており、同様に、諸感覚の感性は、わたしたちがそれであるところの原初的な感性を指し示している。」「あらゆる有機体はその受容的なエレメントにおいても知覚的なエレメントにおいても、またそればかりでなく、その内臓においても、縮約の過去把持の、そして期待の総和なのである。まさにこうした生命の原初的感性の水準でこそ、生きられた現在が、時間においてすでにひとつの過去とひとつの未来を構成しているのである。」「しかも、それらの有機的な総合は、その上に築き上げられた知覚の総合と組み合わされることによって<精神―有機的>な記憶と知能(本能と学習)における能動的な総合のなかで再び展開されるのである。」「したがって私たちは、受動的総合に関連してもろもろの反復形式を区別する必要があるばかりでなく、さらに受動的総合の諸水準を区別し、それらの水準相互のもろもろの組み合わせを区別し、それらの水準と能動的総合とのもろもろの組み合わせをを区別する必要がある。それら一切がしるし(シーニュ)の豊穣な領域を形成しているのであ」る。「それぞれの縮約、それぞれの受動的総合が、ひとつのしるしを構成しており、そしてこのしるしがもろもろの能動的総合のなかで解釈あるいは開示されるからである。」(P123)「習慣が、そこでおのれのまったき一般性を顕示するのであって、その一般性はたんにわたしたちが(心理的に)有している感覚運動的な習慣に関わっているのである。縮約することによってこそ私たちは習慣であるのだが、しかしそれと同時にまた、観照することによってこそ、私たちは習慣をつけるのである。私たちは観照であり、私たちは想像力であり、私たちは一般性であり、わたしたちは要求であり、私たちは満足なのだ。なぜなら要求という現象は、それもまた縮約を遂行する観照に他ならないのであって、この観照を通じてはじめて、わたしたちは自分がつけるもの(習慣)に基ずく自分の権利と期待を肯定するのであり、また観照するものである限りでの自分自身に対する満足を肯定するのである。なるほどわたしたちは自分自身を観照するのではないが、しかしわたしたちはそこから生まれてくる当のもの(習慣)をつけることによってしか存在しないのである。」(P125)「受動的総合という至福が存在するのだ。わたしたちは、自分自身とは、まったく別のものを観照するにせよ、とにかかく観照を遂行することで快感を覚え(自己満足)、そしてこの快感のゆえにこそ私たちはみなナルシスなのである。観照するということ、それは抜き取ることである。おのれを自己自身のイマージュで満たすために、まず始めに、観照しなければならないものは、つねに自己とは別のもの、すなわち、水、ディアナ、あるいは森である。」(p126)
行動における「一般性は反復とはまったく別のことであるにせよ、それでもなお一般性は反復をその一般性がそこで構築される隠れた基盤として指し示しているのである。行動の構成は、一般性のレヴェルにおいても、それに対応した諸変項の場においても、反復の諸要素の縮約によって実現されるほかはないのである。ただし、この縮約は、それ自体において遂行されるのではなく、観照し、そして行動者を裏打ちしている自我のなかで遂行されるのである。」「反復から何か新しいものを抽出すること、反復から差異を抜き取ることは多様で細分化された状態において観照をなす精神たる想像力の役割である。そればかりでなく、反復はその本質からして想像的なものであって、それというのも、ひとり創造力のみが、この場合、(行動の)構成の観点から反復力という「契機」を形成し、おのれが縮約するものを反復の要素あるいは事例として存在させるからである。」(P127)これが反復の対自である。「ひとつの有機体はひとつの現在的持続を所有しており、さらには、有機体内部の観照的なものもろの魂における縮約の自然な射程に応じて様々に異なる現在的持続を所有している。」「欲求と言う現象は、行動の観点からは、また欲求によって規定されるもろもろの能動的総合の観点からは「欠乏」とういう形で理解されるのだが、反対に、欲求の前提条件である受動的総合の観点からは、ある極度の「飽満」、ある「疲労」として理解されうるのである。」「反復は、本質的に欲求の中に刻み込まれているのだ。なぜなら、欲求が成立する審廷は、本質的に反復に関わっており、反復の対自を、つまりある一定の持続の対自を形成しているからである。」「現在に関するしるしすなわち、受動的総合に基づくしるしは、それが意味しているものにおいて現在を指し示しており、これがすなわち自然的なしるしである。」「当の現在が依存してるような次元としての過去と未来を指し示すしるしが人為的なしるし<記号>である。このようなしるしは能動的総合を含意している。すなわち、おのずと働く創造力から、能動的な能力としての反省された表象=再現前化、記憶、知能への移行を含意しているのである。」「自我はみな幼生の主体であり、もろもろの受動的総合の世界は、一定の規定さるべき条件の下で自我のシステムをを構成しているのである。秘めやかな観照がどこかで打ちたてられるや、あるいは反復がまたたくまにひとつの差異を抜き取りうる縮約機械がどこかで作動するや自我というものが存在するのである。」